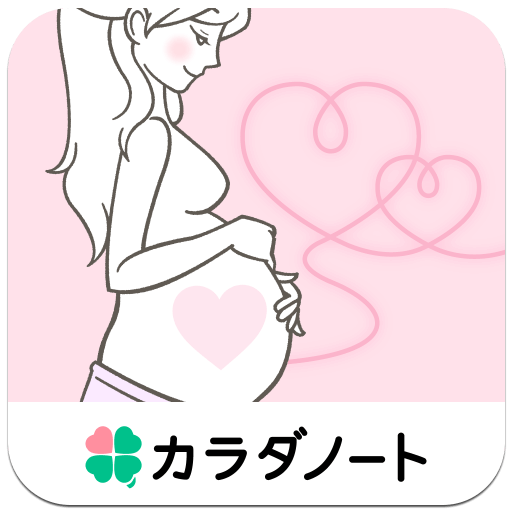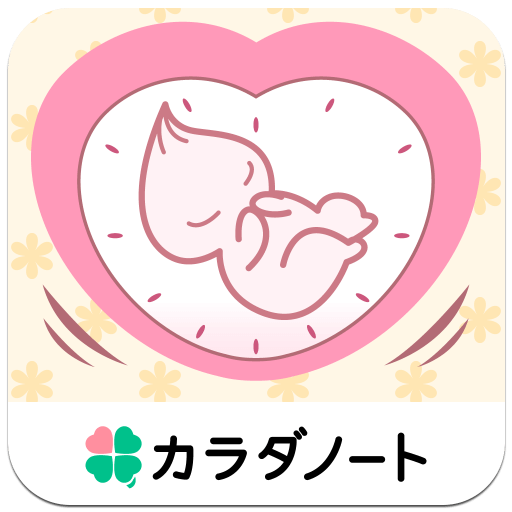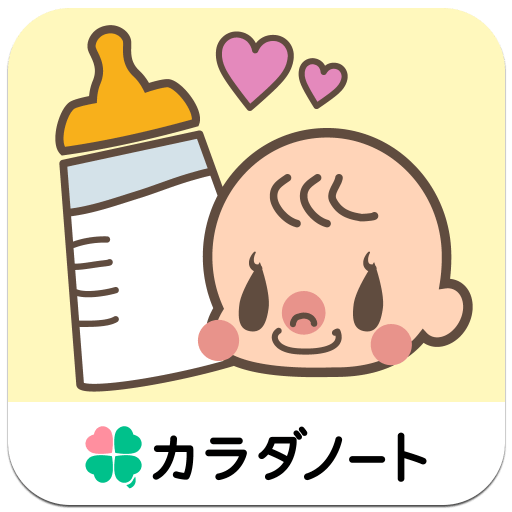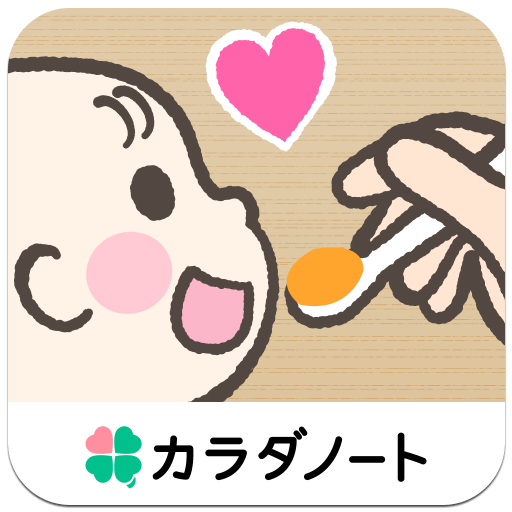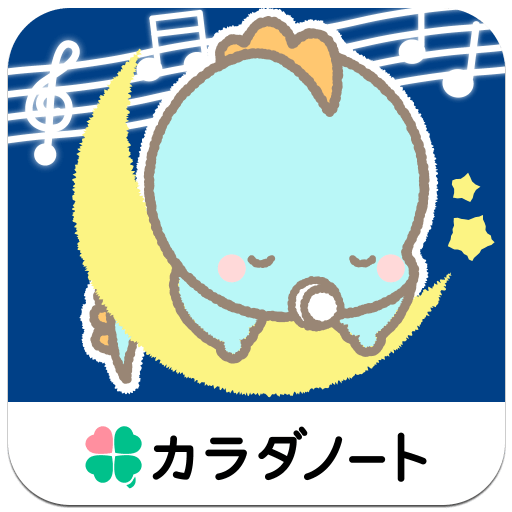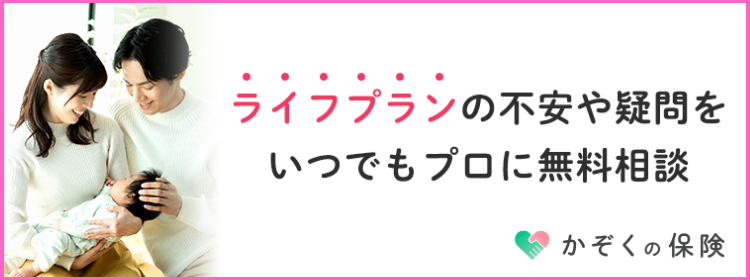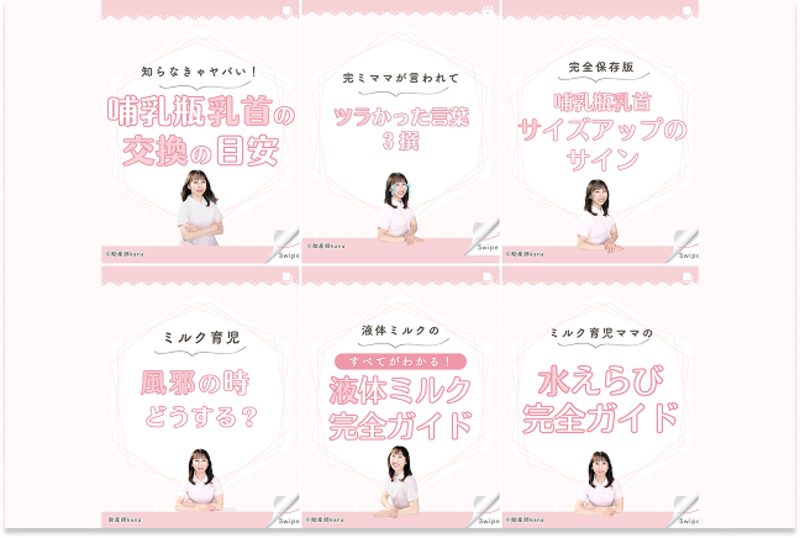
「ミルクでも罪悪感を持たないで。どんな授乳方法を選んでも愛情は変わらないから」
そう優しく語るのは、3年前からミルク育児専門の助産師としてInstagramで情報発信を続ける助産師 kanaさん(mw_kana)。自身の経験から「ミルク育児について、もっと情報が必要」と感じ、多くのママたちの駆け込み寺となるアカウントを立ち上げました。
小学校高学年から抱いた助産師への夢
kanaさんが助産師を目指したのは小学校高学年の頃。母親から自身の出産のことや妹の出産のお話を聞いていたこと、また、いとこを産んだ叔母の出産を見た経験がきっかけでした。
「叔母の出産に立ち会った助産師さんが、陣痛中も産後も本当に上手にサポートしていました。私がまだ子どもだった頃に、叔母と助産師さんのやりとりを近くで感じて、『助産師ってなんてすごいんだ』と純粋に憧れを抱いたんです」
その思いを胸に看護学校、そして助産師学校へと進み、夢を実現させました。
専門家でも直面したミルク育児の情報不足
kanaさんは新卒で母乳育児に特化した総合病院の産婦人科に勤務。そこはWHOとユニセフが認定する「Baby-Friendly Hospital(BFH)」でした。
「母乳育児については専門的な研修を受け、たくさん学ぶ機会がありました。でも意外なことに、ミルク育児に関しては学ぶ機会がほとんどなかったんです」
自身の子育てで息子さんにミルク育児をすることになったとき、専門家である自分でさえ情報が少なく困ったといいます。
「息子がミルクの飲みが悪く、体重も増えずに悩んでいました。小児科や保健師さんに相談しても『ミルクは楽なはずなのに、助産師のくせにできないの?』と言われることもありました」
ミルク育児に関する発信をスタート

kanaさんによると、粉ミルクのマーケティングには規制があるため、ミルク育児に関する情報が限られているという背景があります。
「妊娠中に母乳育児を希望している人は94%もいますが、実際には約半数の方がミルク育児をしています。理想と現実に大きな隔たりがあるのに、サポートが足りていない」
そういった状況を変えたいという思いから、2022年1月にInstagramでミルク育児に関する情報発信を始めました。アカウントには、母乳が出なかった方、医学的な理由でミルク育児を選ばざるを得なかった方、LGBTのカップルなど、さまざまな背景を持つママたちが集まってきます。
「私はミルク育児を推奨しているわけではありません。母乳育児の利点ももちろん理解しています。でも大切なのは、ママと赤ちゃんそれぞれの状況や思いに寄り添うこと。ミルクを選んだことに罪悪感を持つ必要はないんです」
特に反響が大きかった投稿は:
- 「ミルクは3時間空けなくても大丈夫」
- 「赤ちゃんの満腹のサインの見分け方」
- 「1滴でも母乳をあげた経験があるなら、それは母乳育児を頑張ってきた証」
といった実践的な内容や、ママの気持ちに寄り添うメッセージでした。
支援の輪を広げる活動
現在、kanaさんはミルク育児アドバイザー養成講座を開催し、支援の輪を広げる活動に力を入れています。
「私1人が発信するだけでは限界があります。現場で働く助産師さんや看護師さん、産後ケアの支援者さんにミルクの知識を伝えることで、もっと多くのママたちに適切なサポートが届くようにしたい」
そうして3年前に比べると少しずつミルク育児の情報も増えてきましたが、まだまだ母乳育児に比べると少ないのが現状です。
kanaさんからママへ伝えたいこと

最後にkanaさんは穏やかな笑顔で語りかけます。「どんな授乳方法であっても愛情は変わりません。自分の育児に自信を持ってほしい」というメッセージには、多くのママたちが救われてきました。
特にミルク育児に罪悪感を抱きがちなママに向けて、「自分らしくあることも大切」と背中を押します。
育児は思い通りにいかないことの連続ですが、最終的には自分自身のペースで進んでいくことが大切だと教えてくれました。
「育児はそんなにせかせかしなくても何とかなることが多いので、『ぼちぼち行こう』という気持ちでいてくださいね」という言葉には、肩の力を抜いて育児に向き合ってほしいというkanaさんの優しさが詰まっています。
●教えてくれた専門家 助産師 kanaさん(mw_kana)
新卒で総合病院の産婦人科に勤務、その後の妊娠・出産を経て開業した助産師。母乳がうまくいかず悩んだ自身の経験から、現在はInstagramで「どんな授乳方法でも愛情は変わらない」と発信し、ママの不安に寄り添う実践的なアドバイスを届けています。ミルク育児アドバイザー養成講座の主宰や、助産院MOFUの代表も務めています。