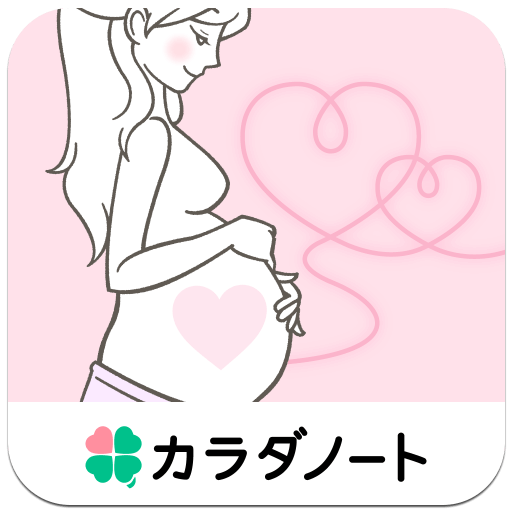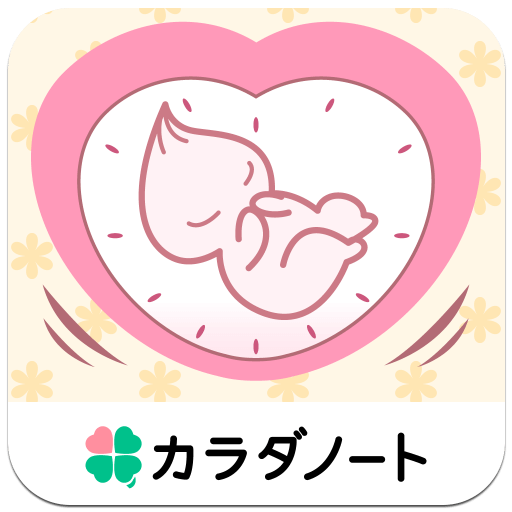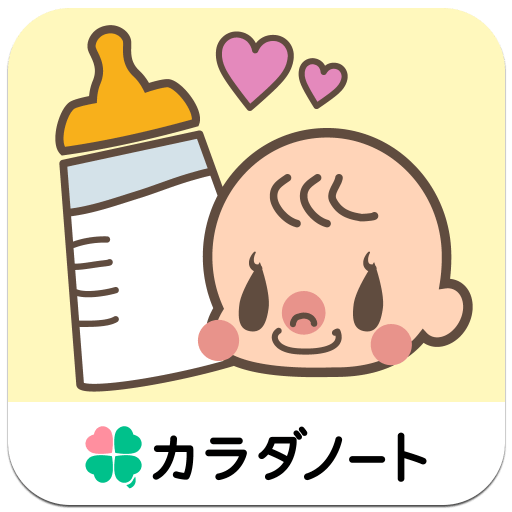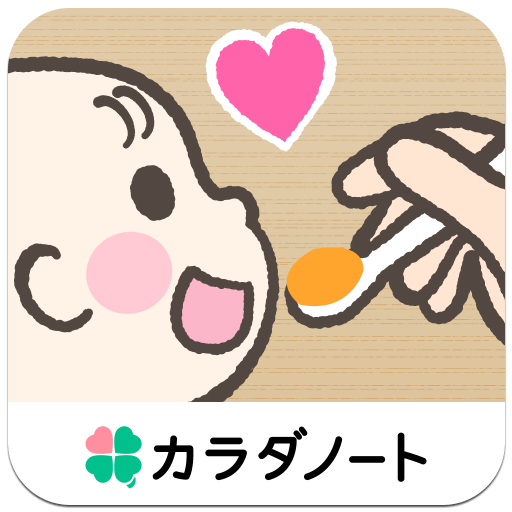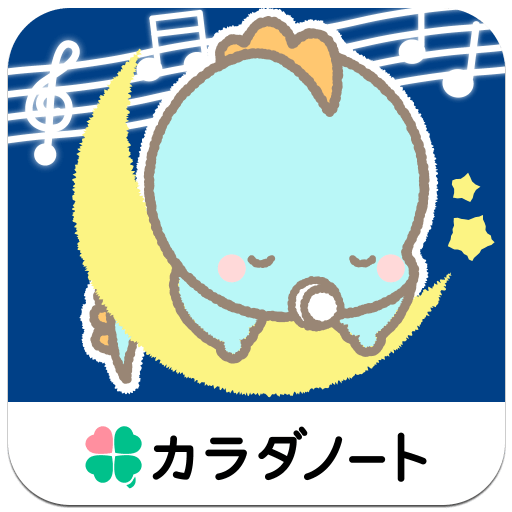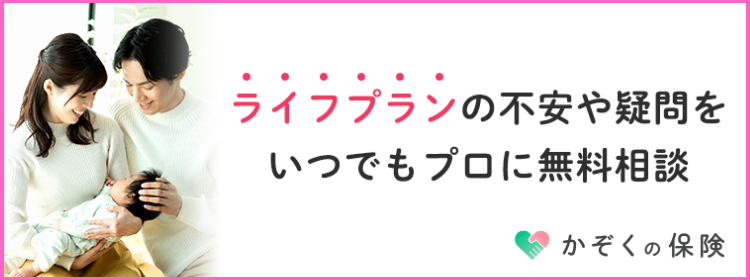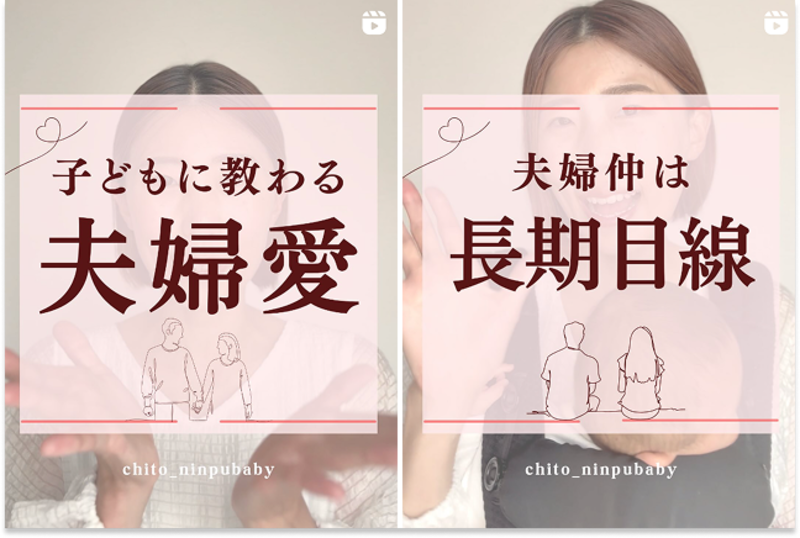
「夫から『俺なんていない方がマシなんやろ』と言われてしまって…。助産師の私でさえ、産後の夫婦関係でこんなに悩むんだから、一般のママはもっと大変だろうな」
産後の夫婦関係の改善をテーマにInstagramで発信し、多くの共感を集めているちとママさん(chito_ninpubaby )。2人の子ども(3歳と6ヶ月)を育てながら、自身の経験をもとに「赤ちゃんが産まれた後の夫婦のすれ違い」に悩むママたちをサポートしています。
理想と現実のギャップに苦しんだ産後の日々

小学生の頃から助産師を志し、赤ちゃんの誕生に立ち会う喜びを感じていたちとママさん。しかし自分が母親になったとき、想像していた幸せな家族の姿とは違う現実が待っていました。
「子どもが生まれたら、もっと家族として仲良くなって、もっと幸せになれると思っていたのに…どうしてこんなに私たち夫婦の空気が悪くなってしまったんだろう」
長女が生後8〜9ヶ月の頃がピークだったと振り返ります。実家から遠く離れた場所での育児。社会から切り離されたような孤独感。そして、仕事という「認められるもの」がある夫への羨望。
「私は家事育児したって誰からも評価されない」
「私だけが頑張っている」
「なんで夫はもっと手伝ってくれないの?」
そんな思いを抱えながら、不機嫌さをぶつけ続けた結果、夫との関係はどんどん悪化。ギスギスした空気が常に漂うような状態になっていきました。
気づいたのは「原因は相手だけではなく、私にもあった」ということ
転機が訪れたのは、長女が1歳半頃。自己理解と他者理解を深める講座に参加したことがきっかけでした。
「気づかせてもらったんです。全部が全部私じゃないけど、私にも原因があるって」
特に大きかったのは、次の気づきでした:
●自分の求めるハードルが高すぎた
●夫がやってくれたことに素直に感謝できていなかった
●自分の感情の扱い方を知らなかった
「相手のせいにするのは簡単。でも、それじゃ何の解決にもならないし、自分も幸せになれない」
徐々に夫婦関係が改善していく中で、ちとママさんは「産後の夫婦関係で悩むのは私だけじゃない」と気づきます。そして、自分の経験を活かして他のママたちを助けたいという思いから、Instagramでの発信を開始しました。
助産師としての視点で見つけた「産後夫婦のすれ違い」の本質
ちとママさんが指摘する産後の夫婦関係における最大のすれ違いポイント。それは「愛情の向け方の違い」です。
「ママたちは子どもが第一になるのが当たり前だと思っています。子どものために調べて、子どものためにすべてを捧げる。それが愛情だと。でも、パパたちは子どもが生まれたからこそ仕事を頑張らなきゃと思っている人が多い。一家の大黒柱として家族を養うことが自分の役割だと」
どちらも「家族のため」という同じ目的なのに、その表現方法が違うために生じるすれ違い。ちとママさん自身も「毎朝仕事に行って、ちゃんと家に帰ってくるという行為自体が大きな愛情表現だということに気づかなかった」と言います。
夫婦関係を改善するための実践ポイント

夫婦の仲を改善するにはどんなポイントがあるのか、ちとママさんが教えてくれました。
1.自分が感謝されたいなら、先に感謝の気持ちを伝える
夫の当たり前の行動にも感謝を表現することで、自分の家事育児も当たり前ではなく感謝されるものに変わります。
2.手放す勇気を持つ
「これは今しないといけないことなのか」「やらないと死ぬのか」というレベルで考えて、完璧を求めすぎないこと。
3 自分の苦手なことを素直に認める
「料理が苦手」など、自分の弱みを隠さず夫に伝えることで、互いの理解が深まります。
4.頼る力をつける
一人で抱え込まず、周りの人や制度を活用する力も大切です。
5.コミュニケーションを怠らない
子どもが生まれると夫婦のコミュニケーションの時間は圧倒的に減るからこそ、聞く努力・伝える努力が必要です。
産後の夫婦関係を改善するために大切なこと
ちとママさんが産後の夫婦関係に悩むママたちに伝えたい一番大切なメッセージは、意外にも「自分を大切にすること」です。
「産後のママは自分のことを後回しにしすぎ。自分は我慢して子どもを最優先にしているのに、夫は子どもが生まれても自分中心だから、それにイライラして夫婦関係がどんどんこじれていくんですよね」
「子どもよりも夫よりも、まずは自分が大切なんだよ」
この言葉は、決して自己中心的になれということではありません。むしろ、自分を大切にできる余裕があってこそ、周りの人にも愛情を注げるようになるという意味なのです。
「赤ちゃんを一日中家で育てているだけですごいこと。それを自分で認めてあげてほしい」
自分を責めたり、SNSの理想的な投稿と比較して自己肯定感を下げる必要はありません。ちとママさんは「SNS発信者として言えるのは、投稿は生活の一部を切り取っただけ。答えがそこにあるわけじゃない」と強調します。
妊娠中からの予防的アプローチへ

ちとママさんは今後、産後だけでなく妊娠中のママたちへも、夫婦関係に関する知識を広めていきたいと考えています。
「産後の夫婦仲がギスギスしやすいこと、ママがいっぱいいっぱいになることが夫婦関係に影響することを、もっと妊娠中から伝えていきたい」
また、企業と連携した講義の実施や、父親支援の範囲拡大も視野に入れています。
「父親支援がもっと幅広くできるようになれば」という思いは、助産師学生時代から持ち続けている夢でもあります。
小さな子どもたちを育てながら、自らの経験を力に変えて多くのママたちを支援するちとママさん。彼女の言葉には、専門知識だけでなく、当事者としての痛みや気づきが詰まっています。
「お母さんが笑顔だったら、家族皆が笑顔になる」
あなたの笑顔が家族の幸せにつながる—そんなちとママさんからのメッセージを、ぜひ日々の育児の中で思い出してみてください。
●教えてくれた専門家 ちとママさん(chito_ninpubaby )
3歳と6ヶ月の2児の母。小学生の頃から助産師を志し、病院勤務を経て現在はInstagramで産後の夫婦関係改善に関するコンテンツを発信。自身の経験をもとに、「産後の夫婦仲で悩むママたち」向けに講座も開催している。